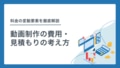動画制作の流れとスケジュール管理の完全ガイド|目安の期間や交渉術も紹介
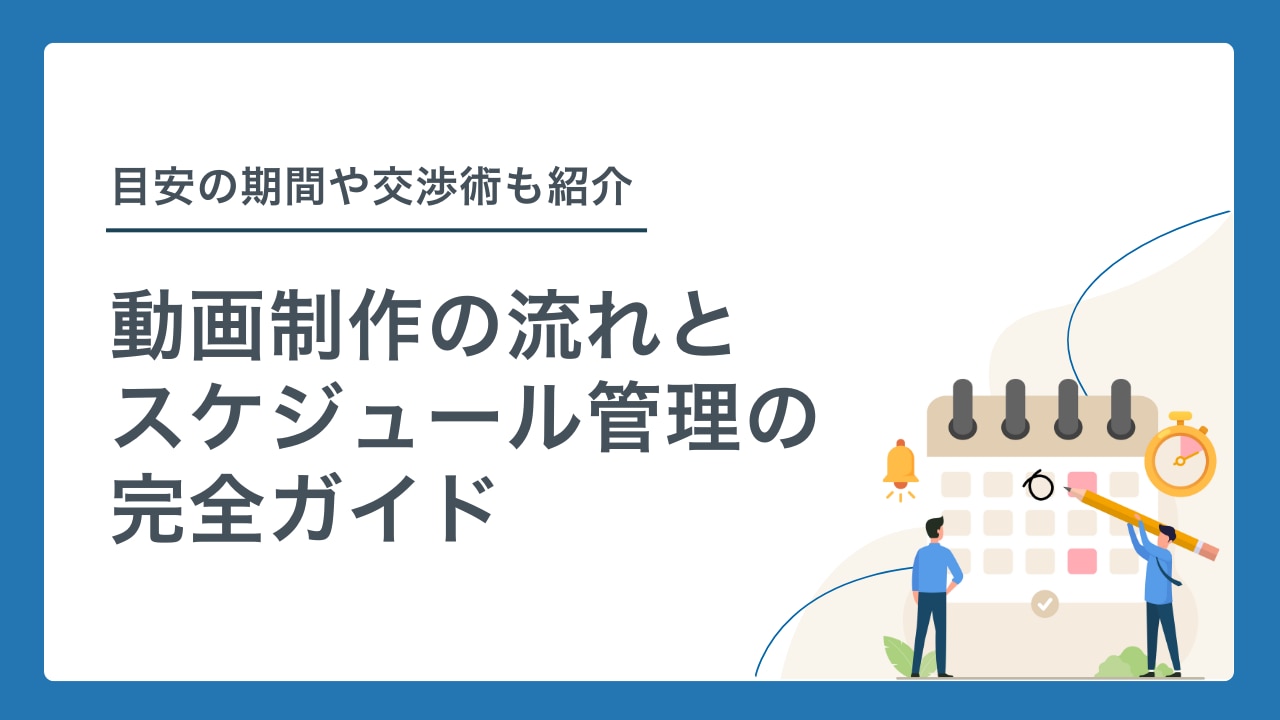
「動画制作を任されたけど、何から手をつけていいか分からない …」「全体の流れや、完成までにどれくらいの期間がかかるのか見当もつかない」
初めて動画制作の担当者になった方の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
動画制作は、専門的な知識や経験が必要に思われがちですが、全体の流れと各工程でのポイントを理解すれば、決して難しいものではありません。
この記事では、動画制作の全体像から具体的なスケジュール、そして制作をスムーズに進めるための注意点まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。
また各ステップでの具体的なアクションや、よくある失敗事例も交えながら、あなたの動画制作プロジェクトを成功に導きます。
▼あわせて読みたい
動画制作を依頼する際に気を付けるポイントについて解説
目次[非表示]
まずは全体像を把握!動画制作の3つの工程と期間の目安
まずは動画制作の全体的な流れやポイントを押さえてみましょう。
全体の流れをざっくりと捉えることは、スケジュールを管理する上で非常に重要です。
各工程の作業ボリュームや必要となるリソースを把握しておくと、無理のない計画が立てやすくなります。
また、取りかかりの時点で明確な工程イメージをあらかじめ共有しておくと、関係者との連携ミスを防ぎ円滑に作業を進めることができます。
動画制作は 3つの工程で進む

動画制作は、以下の3つの主要な工程(フェーズ)に分かれています。
- 企画フェーズ:
動画の目的を定め、どのような企画・内容にするかを決める最も重要な工程です。ここでプロジェクトの土台を固めます。 - 撮影・素材制作フェーズ:
企画内容を元に、実写動画であれば撮影を行い、アニメーション動画であれば、イラストを作成する工程です。
企画という設計図をもとに、編集をするために必要な素材を集める段階です。 - 編集・納品フェーズ:
撮影した映像や素材を繋ぎ合わせたり、テロップやBGMなどを加えて一本の動画として完成させる工程です。
制作期間の目安は 1ヶ月~ 2ヶ月
制作する動画の内容によって期間は大きく変動しますが、一般的な制作期間の目安は以下のとおりです。
- 撮影がある実写動画の場合: 約1.5ヶ月〜2ヶ月
- 例:社員インタビュー、会社紹介、商品・サービス紹介など
- 撮影がないアニメーション動画の場合: 約1ヶ月〜1.5ヶ月
- 例:サービス紹介動画、マニュアル動画、インフォグラフィック動画など
状況によりこれより短くなることも長くなることもありますが、まずは一つの目安として考えてください。
例えば、実写動画でも複数のロケ地でドラマ仕立ての動画を作る場合などは撮影にも時間がかかるため、3ヶ月以上かかることもあります。
一方で、撮影が必要最低限のインタビュー動画などであれば2~3週間ほどで納品することもあります。
企画の複雑さ、修正の回数、関係者の確認スピードなど、多くの要因が絡み合って最終的なスケジュールが決まるということは、意識しておいてください。
それでは各フェーズで具体的にどのような流れで進んでいくか、担当者は何に注意すればよいかなどを見ていきましょう。
企画フェーズの流れと作業内容
動画のコンセプトやメッセージを固める重要な段階です。
このフェーズでは、どのようなメッセージを視聴者に伝えたいのかを具体化し、全体の方向性を決定します。
企画が曖昧なまま撮影や編集に進んでしまうと、仕上がりがブレて大幅な作り直しが発生しやすくなります。
逆に、練り込まれた企画があれば、後の工程で必要となる素材やカットが明確になり、スケジュール管理もスムーズになります。
Step1.打ち合わせ・ヒアリング(キックオフ MTG)
最初の打ち合わせでは、制作会社とクライアントが顔を合わせ、プロジェクトの全体像を共有します。
一般的に「キックオフミーティング」と呼ばれるこの打ち合わせでは、以下の項目を主に確認します。
- 動画制作の目的(何のために作るのか)
- ターゲット層(誰に見てもらうのか)
- 配信媒体(どこで公開するのか)
- 予算の確認
- 納期の設定
- 制作スケジュールの概要
- 企画の方向性やイメージの確認
【担当者チェックポイント】
- 動画制作の目的(Why)は明確か?:
何のためにこの動画を作るのか、制作会社と目線を合わせましょう。
「新サービスの認知度を上げたい」「採用サイトからのエントリー数を1.5倍にしたい」など、
できるだけ具体的なゴールを設定することが重要です。
「カッコいい動画を作りたい」といった曖昧な目的では、判断基準がブレてしまいます。 - 要望は具体的に伝えられているか? :
参考動画(ベンチマーク)を 2~ 3本提示し、「この動画の冒頭のテンポ感が好き」「こちらの動画の色味が理想」といったように、
具体的にどこが良いのかを伝えられると、イメージの共有が格段にスムーズになります。
Step2.企画・構成案の作成
キックオフミーティングの内容を元に、制作会社が動画の骨子となる企画・構成案を作成します。
動画全体のメッセージや、どのような流れでストーリーを展開していくかをテキストベースでまとめたものです。
【担当者チェックポイント】
構成案を確認する際は、「この内容で目的を達成できるか」「ターゲットに響く内容になっているか」を必ず確認しましょう。
また、社内の関係者にも早めに共有し、意見を集約しておくことが重要です。
Step3.シナリオ・絵コンテの作成と FIX
構成案の合意が取れたら、より具体的なセリフやナレーションを記した「シナリオ(台本)」や、映像のイメージをイラストや写真でコマ送りのように示した「絵コンテ」を作成します。
絵コンテによって、完成する動画のイメージがより明確になります。
制作会社から提出されたシナリオや絵コンテに対し、依頼主側で内容を確認し、修正の要望をフィードバックします。
この「提出 →チェック →修正」というやり取りを通常 2回ほど繰り返し、内容を固めて( FIX)いきます。
この段階での FIXが、後の手戻りを防ぐために非常に重要です。
【担当者チェックポイント】
- 伝えたいメッセージが表現されているか?:
当初設定した目的からズレていないか、メッセージはターゲットに響く言葉や表現になっているかを確認します。 - 企業のブランドイメージと合っているか?:
動画のトーン&マナー(真面目、親しみやすい、先進的など)が、自社のブランドイメージを損なうものになっていないか、慎重にチェックしましょう。
撮影・素材制作フェーズの流れと作業内容
企画内容をもとに、撮影やイラスト制作などの実際の制作を進める段階です。
ここでは企画フェーズで作成されたシナリオや絵コンテを基に、撮影やイラスト制作などを行います。
実写かアニメーションかによって必要な工程は異なりますが、いずれにしても準備段階がスムーズであるほどトラブルを防ぎ、スケジュールを守りやすくなるのが特徴です。
撮影場所の確保や出演者とのやり取りなど、時間のかかる作業も多いため、余裕を持った調整が欠かせません。
ここからは、実写動画とアニメーション動画に分けて解説します。
【実写動画の場合】
実写動画では、ロケ地や撮影機材の選定、出演者の手配などの事前準備が重要になります。
特に撮影日程は出演者やスタッフの都合を踏まえる必要があるため、複数の候補日を用意しながら計画を進めるとスムーズです。
また、撮影スケジュールがタイトな場合は、撮影後の編集に影響するため、撮影対象と狙いたいカットを事前にリストアップして効率的に行いましょう。
Step4. 撮影準備(出演者・ロケ地の手配)
FIXしたシナリオ・絵コンテを元に、撮影に向けた具体的な準備を進めます。
- 出演者のキャスティング :
役者やモデル、社員など、動画に出演する人物を手配します。社員に出演を依頼する場合は、事前に十分な説明と協力を仰いでおくことが重要です。 - ロケ地の選定(ロケハン) :
動画の雰囲気に合った撮影場所を探し、使用許可を取得します。
オフィスで撮影する場合は、撮影当日に通常業務の支障が出ないよう、社内調整が必須です。 香盤表・撮影機材の準備:
当日の撮影スケジュールや出演者の入り時間などを詳細に記した香盤表を作成し、必要なカメラや照明、音声機材を手配します。
【担当者チェックポイント】
撮影協力:
撮影に必要な備品(商品、制服、 PCなど)の準備や、撮影場所の整理整頓、関係部署への事前通達など、依頼主側の協力が不可欠です。
制作会社任せにせず、積極的に連携しましょう。
Step5. 撮影・収録
いよいよ撮影本番です。
会社紹介動画の場合、通常 1日の撮影で完了することが多いですが、複数の場所での撮影や、多くのシーンがある場合は 2~ 3日かかることもあります。
撮影当日の流れ:
機材搬入・セッティング(1〜2時間)
リハーサル(30分〜1時間)
本番撮影(3〜6時間)
撤収( 1時間)
【担当者チェックポイント】
撮影現場には必ず立ち会い、その場で確認できることは確認しましょう。
「もう少し明るい表情で」「この角度から撮影してほしい」など、後から修正が難しい要素は、撮影時に調整することが重要です。
【アニメーション動画の場合】
アニメーション動画では、キャラクターデザインや背景イラスト、グラフィック素材の制作が主な作業となります。
実写と比べて撮影の手間は少ないものの、その分イラストレーターやアニメーターのクリエイティブ作業時間が必要です。
キャラクターや素材が完成したら、後述するアニメーション編集工程に移行します。
Step4.イラスト・各種素材の制作
この工程では絵コンテをもとに、キャラクターイラストや背景、アイコンなどを具体的に作り込みます。
制作する素材が多い場合は、タスクを細かく切り分けて進捗を管理し、関係者同士でスピーディーにチェックを行うことがポイントです。
完成したデザインは、アニメーションソフトで動きを付ける準備に回されます。
【担当者チェックポイント】
イラストのテイストは、初期段階でサンプルを確認し、方向性を固めましょう。
「もっとポップに」「もっとシンプルに」といった抽象的な指示ではなく、参考となる画像を共有すると、イメージの齟齬を防げます。
Step5.アニメーション編集
必要なイラスト素材が揃ったら、アニメーションソフトを使って実際に動きを付けていきます。
ここでは演出効果を追加しながら、キャラクターの動きを自然に見せるための微調整作業が続きます。
完成が近づいたら仮ナレーションや BGMを入れ、映像の雰囲気を最終確認しながら次の編集・納品フェーズへと進めていきます。
編集・納品フェーズの流れと作業内容
素材を最終的に編集し、完成映像へと仕上げる工程です。
この段階では、撮影した映像や制作したアニメーション素材をつなぎ合わせ、 BGMや効果音を組み込むことで動画の全体像が完成します。
編集の完成度は動画のクオリティを大きく左右するため、試写を行いながら細かい修正点を洗い出していくのが一般的です。
最終チェックを経て問題がなければ、依頼主の希望に沿った形式で納品されます。
Step6. 編集と試写(初稿チェック)
撮影した映像や制作したアニメーション素材を、シナリオに沿って繋ぎ合わせる「オフライン編集(仮編集)」を行います。
その後、テロップや簡単なBGMなどを加えた「初稿」が完成します。
依頼主は、制作会社から提出された初稿映像をチェックし、修正点をフィードバックします。
ここでも企画段階と同様に、通常 2回程度の修正のやり取りが発生します。
【担当者チェックポイント】
- 修正指示は具体的に :
曖昧な指示は、意図が伝わらず修正のやり直し(再修正)を招きます。
誰が見ても分かるように、具体的かつ定量的に指示を出すことが重要です。
▼ 効果的な修正指示の文例- 悪い例: 「ここの部分、もっとカッコよくしてください」
- 良い例: 「【1分15秒〜1分25秒】のBGMを、参考動画Aで使われているような、もう少しアップテンポな曲に変更してください。また、テロップのフォントをゴシック体から明朝体に変更してください。」
- 修正依頼は一度にまとめる :
関係者全員の意見を一度に取りまとめ、リストにしてフィードバックするのが最も効率的です。
個別にバラバラと指示を出すと、制作会社が混乱し、作業が滞る原因になります。
Step7. 音入れ・ナレーション収録(MA)
映像の修正が完了したら、音に関する最終的な仕上げを行います。
MA( Multi Audio)とは、ナレーション、 BGM、効果音などを映像に合わせて調整し、全体の音のバランスを整える作業です。
適切な BGMや効果音は、視聴者の感情に訴えかけ、動画のメッセージをより強く印象付けます。
プロのナレーターによるナレーション収録もこの段階で行います。
【担当者チェックポイント】
ナレーションの別日での再収録には、追加で費用が発生するケースが多いです。
企業名や商品名の読み方、アクセントの位置など、事前に確認しておき、収録時に指摘ができるようにしておきましょう。
Step8. 最終チェックと納品
すべての要素が揃ったら、最終確認を行います。
最終チェック項目:
- 映像と音声のタイミング
- テロップの誤字脱字
- 企業ロゴやコピーライトの表示
- 全体の色味や音量
- 納品形式(ファイル形式、解像度など)
問題がなければ、指定された形式で納品となります。
YouTube用、Webサイト埋め込み用、展示会用など、用途に応じて複数の形式で納品されることもあります。
【担当者チェックポイント】
最終確認は、実際に動画を使用する環境(スマートフォン、 PC、プロジェクターなど)でも確認することをおすすめします。
デバイスによって見え方や聞こえ方が異なる場合があります。
展示会などイベントで使用する場合は、当日に気づいても修正が間に合わない場合がありますので特に注意が必要です。
【要注意】動画制作でスケジュールが遅延する主な原因と対策
計画通りに動画制作を進めるためには、遅延の原因となりがちなポイントを事前に把握し、対策を講じることが重要です。
ここでは、よくある失敗事例を交えて解説します。
原因1:企画や構成のFIXに時間がかかる
【失敗事例】
あるメーカーで新商品のプロモーション動画を制作。
マーケティング部、営業部、開発部でそれぞれ動画に求めるものが異なり、構成案の修正が 5回以上も発生。
「営業は機能を詳しく説明しろと言うし、マーケはとにかくインパクト重視。
板挟みで全く決まらなかった …」結果、企画だけで 1ヶ月半を要し、商品発売のタイミングに動画公開が間に合わなかった。
対策:
- プロジェクトの最高責任者を明確にする:
関係部署が多い場合は特に、最終的な意思決定者を一人に定め、その人の判断を絶対とすることを事前に周知徹底します。 - キックオフ MTG で目的の合意形成を :
企画段階で、動画の目的とターゲット、絶対に伝えたいコアメッセージを関係者全員で共有し、そこから逸脱しないという共通認識を持つことが不可欠です。
原因2:関係者の確認・フィードバックが遅れる
【失敗事例】
BtoB企業のサービス紹介動画を制作。
担当者はスムーズに制作会社とやり取りしていたが、最終承認者である役員の確認がいつも遅れがち。
「役員が出張続きで捕まらず、初稿チェックに 1週間もかかってしまった …」
その遅れが響き、予定していた展示会での初披露に間に合わせるため、編集作業を極端に短縮せざるを得ず、クオリティに妥協が残る結果となった。
対策:
- 関係者のスケジュールを事前にブロックする:
制作スケジュールが決まった段階で、承認者を含む関係者全員に「〇月〇日〜〇日は動画の確認期間です」と伝え、カレンダーを抑えてもらいましょう。 - 確認の役割分担を明確にする :
「 Aさんはメッセージの内容を、 Bさんはデザインのトンマナを、 Cさん(法務部)は薬機法などの表現をチェックする」というように、誰が何を確認するのかを事前に定義しておくと、確認作業がスムーズに進みます。
原因 3:予期せぬ修正や追加要望が発生する
【失敗事例】
ある IT企業で採用動画を制作。
編集がほぼ完了した最終チェックの段階で、社長から「やっぱり、新しくできた福利厚生制度も入れたい」という鶴の一声が。
その制度を説明するには追加の撮影が必要となり、結果的に 1ヶ月のスケジュール延長と、数十万円の追加費用が発生してしまった。
対策:
- 各工程の「FIX」の重みを共有する:
「この絵コンテでFIXしたら、これ以降のストーリー変更は原則不可です」というように、各工程での決定の重要性を関係者全員に理解してもらうことが重要です。 - 変更・追加要望のルールを設ける :
予期せぬ要望に備え、「構成 FIX後の修正は追加費用が発生します」「修正指示は 2回までです」といったルールを、事前に制作会社と握っておきましょう。
スケジュール管理を成功させるための交渉術と注意点
どうしても納期を早めたい場合、闇雲にお願いするのではなく、具体的な交渉材料を持って臨みましょう。
- 制作会社の作業期間を短縮してもらう(費用増) :
「編集作業に人員を追加投入してもらうことは可能でしょうか。
その場合の追加費用を教えてください」といった交渉が考えられます。これは、いわゆる「特急料金」による調整です。 - 自社のチェック期間を短縮する(費用そのまま) :
「弊社の確認期間を通常 3営業日のところ 1営業日に短縮します。
その分、 2日納期を早めていただくことは可能でしょうか?」という交渉も可能です。
この提案をするには、社内の迅速な確認体制を整えることが大前提となります。
やみくもな納期短縮依頼は品質低下のリスクがある
動画制作はクリエイティブな要素が多いため、単純に時間を減らすと表現やクオリティに影響を受けます。
映像の完成度を優先するのであれば、十分な検討時間と修正回数が必要なのは事実です。
なるべく余裕を持った日程を確保し、やむを得ない場合でも妥協できる範囲を明確にしてから交渉を進めましょう。
補足:失敗しない動画制作会社の選び方
良いパートナーとなる制作会社を選ぶことは、スケジュール通りに質の高い動画を完成させるための最も重要な要素です。
以下のポイントを参考に、自社に合った会社を選びましょう。
実績は豊富か? - ポートフォリオの「質」と「量」をチェック
自社が作りたい動画のジャンル(例:採用動画、商品紹介動画など)での制作実績が豊富かを確認しましょう。
単に本数が多いだけでなく、 どのような課題に対し、どのような動画で応え、どんな成果が出たのか、というストーリーまで語れる会社は信頼できます。
Webサイトに掲載されている実績だけでなく、可能であれば非公開の実績も見せてもらうと良いでしょう。コミュニケーションは円滑か? - 「翻訳力」と「提案力」を見極める
担当者のレスポンスの速さはもちろん重要ですが、それ以上に「曖昧なイメージを言語化し、形にしてくれるか(翻訳力)」 、そして「プロの視点から、より良くなるための代替案やプラスアルファの提案をしてくれるか(提案力)」が重要です。
最初の打ち合わせで、こちらの意図を正確に汲み取り、的確な質問を返してくれるかを見極めましょう。スケジュールや見積もりの透明性は高いか? - 詳細な内訳を確認
良い制作会社は、詳細なスケジュール表(ガントチャートなど)や、内訳が明確な見積書を提示してくれます。
「動画制作一式」のような大雑把な見積もりではなく、「企画構成費」「撮影費(カメラマン、機材費など)」「編集費」「 MA費」といったように、項目ごとに費用が明記されているかを確認しましょう。
これにより、どこにコストがかかっているのかが明確になり、予算に応じた調整もしやすくなります。
▼ その他制作会社を見極めるための質問リスト
弊社の業界での制作実績はありますか?
御社の得意な動画のジャンルは何ですか?
プロジェクトの進行は、どのような体制(担当者、ディレクターなど)で行いますか?
修正の回数に制限はありますか?また、追加修正の場合の費用感を教えてください。
動画公開後の効果測定や活用方法についても相談可能ですか?
まとめ
本記事では、動画制作のスケジュールと流れについて、具体的な事例やノウハウを交えながら網羅的に解説しました。
- 動画制作は「企画」「撮影・素材制作」「編集・納品」の3工程で進む
- 制作期間の目安は、撮影ありで1.5〜2ヶ月、アニメーションで1〜1.5ヶ月だが、内容により大きく変動する
- 遅延を防ぐには、関係者間の迅速な合意形成と、具体的でまとまったフィードバックが鍵
- 納期交渉は、制作プロセスを理解した上で、何を譲歩できるかを明確にして建設的に行うことが重要
動画制作の全体像と各工程のポイントを深く理解することで、スケジュールの見通しが立ち、関係者とのやり取りもスムーズになります。
この記事が、動画制作プロジェクトを成功に導く一助となれば幸いです。
LOCUSの紹介
いかがでしたでしょうか。
弊社では、これまで 20,000本以上の動画制作実績があり、様々な企業のニーズに対応することができる動画制作・動画コンサルティングサービスを提供しています。
動画活用、動画制作・映像制作にお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

監修者
渡邊 友浩(株式会社LOCUS 事業推進グループ チーフ)
2017年、動画制作・動画マーケティング支援を行うLOCUSに入社。営業としてBtoB/BtoC問わず累計80社以上の動画活用を支援。現在は事業推進グループとして、宣伝会議やデジタルハリウッドSTUDIOをはじめ、企業・団体向けセミナーで多数登壇。現場で培った経験をもとに、企業のYouTube活用やブランディング動画など、動画マーケティングの戦略立案と実践的な活用ノウハウを発信し続けている。