
YouTubeやTikTok、Facebookなど各SNSの仕様やメリット・デメリット、動画機能について解説
SNS利用者の総数は、世界で46億人を突破し、国内では8000万人を越えています。国内総人口が1億2000万人ですから、実に人口の7割以上がSNSを利用していることになります。テキストや写真だけでなく動画配信機能も各SNSで実装されていて幅広い用途で活用されています。
世界的には、Facebook、YouTubeやTwitterの人気が高いですが、国内ですとLINEの利用者が多い傾向に国内で一番利用者数の多いSNSとなります。
もはやSNSは、情報メディアとしてもコミュケーションツールとしても社会生活をおくる上で欠かせないもののひとつであり、テレビや新聞などの既存メディアや家電話が成していた機能をも内包する主要なツールとして利用されています。
情報発信や広告宣伝ツールとしてももはや主要媒体として認知されており、さまざまな利用価値に焦点が充てられています。
これらのSNSの利用する上での、そしてビジネスシーンで利用する場合のメリット・デメリットを紹介していきます。
▼あわせて読みたい
YouTubeチャンネルの登録者を増やすための6ステップ・24のチェックリスト
SNSとは?

SNSというのは、英語で「Social Networking Site」の略です。日本語では、会員制交流サイトと呼びます。要するにログインして入り、個人同士がネットワーク上でやりとりするプラットフォームを広くSNSと呼びますが、最近はウェブメディアと混在したYouTubeやTikTokもSNSと呼ぶ傾向にあります。
YouTubeやTikTokはどちらかといえば、個人同士のやりとりよりは、インフルエンサーとファンが相対するウェブメディアと見る向きもありますが、コメントしたり投げ銭をする機能があったりと、SNSとしての機能も付随しているため、必ずしもメディアと一言で括れない側面があります。
また、LINEのようなオンラインコミュニケーションツールにもSNS投稿機能がついており、メッセージアプリとして利用しながらも、その延長線上にあるSNS機能にも手を伸ばしやすいということから、多くのユーザーがSNSとしても多用しています。
動画系SNS
YouTubeやTikTokなど、動画配信を主体にしたSNSは、世界中で圧倒的人気を誇ります。コンビニエンスで受動的に情報を得ることができる動画ビジネスには大きな需要があります。
YouTube

▼仕様
主に動画視聴を目的としたウェブメディアとして機能しています。特に配信時間制限はなく、1分の動画もあれば、数時間に及ぶ動画もあります。幼児や子供向けの動画で人気に火が点きましたが、最近はビジネスパーソン向けにビジネスや健康、料理、趣味に関する動画も人気があります。
業者やプロの動画編集者ではなく、素人がスマホなどで撮影、編集したリアリティのある映像が、視聴者にとっては臨場感のある魅力的なコンテンツとして人気を博しています。
昨今は、いわゆるYouTuberと呼ばれるインフルエンサー個人が自分自身をコンテンツとして発信するチャンネルばかりでなく、本の解説や都市伝説、時事ニュースなどをコンテンツとして配信する一般メディアと同等のチャンネルも配信され、40-50代の利用者も増えてきています。
▼SNS機能
動画コンテンツにはコメント欄がついており、自分が支持するYouTuberや魅力的なコンテンツに対して意見や賛辞を述べることができます。時にYouTuber本人からレスポンスされることもあり、相互のやりとりが可能なSNSとしての機能もあります。
ライブ配信の機能もあり、投げ銭でYouTuberを応援することもできます。ライブ配信中は、リアルタイムでコメントを入力することができ、配信しているYouTuber本人もリアルタイムで返信することで相互でコミュニケーションを取れるプラットフォームとしての利用価値が高まっています。
▼デメリット
FacebookやTwitterに比べると相互コミュニケーションすることに重点を置いてはおらず、どちらかというと配信メディアとしての機能が主体になります。
また、個人の情報配信であるため、必ずしもしっかりとしたファクトチェックがなされてないことも多く、真偽が定かではない情報が溢れかえることも多い側面があります。しかし、必ずしもマスメディアの情報に間違いがないとも言いづらく、多様な情報を取捨選択して自身で判断をすることで事実の落としどころを見つけることが重要です。
時に炎上ネタや、過激なコンテンツに埋没すると、ネガティブな情報に執着しすぎてメンタルに支障をきたすこともあります。動画コンテンツというのは、文字や紙メディア以上に依存性が高く、中毒的に見続けてしまう側面もあります。十分に距離感を測りながら、適度に楽しむことが肝要です。
▼ビジネス面
YouTubeには、収益化させて稼ぐというビジネスチャンスと、宣伝広告媒体として利用するというふたつの大きなビジネス利用ができます。
収益化は、再生数を伸ばすことで実現できます。チャンネル登録者数が1,000人以上、直近12ヶ月の総再生数が4,000時間以上を超えると収益化できるようになります。YouTube視聴者にとって魅力的なコンテンツを配信したり、フォロワーの多いYouTuberとコラボしたりすることで、チャンネル登録者数や再生数を増やすことができます。
動画の再生数のみならず、ライブ配信による投げ銭や、タイアップ動画の案件を引き受けることによってさまざまな収益を作ることができるのです。
TikTok

▼仕様
近年勢いを増して利用者が増え続け、縦型のショート動画の投稿に特化したSNSがTikTokです。短い動画をカジュアルに流し見できることだけでなく、フリックすることでザッピングするように動画を見ることができるのが特徴です。
このTikTok特有の縦型ショート動画の隆盛は、他のSNSにも影響を及ぼし、今やYouTubeやFacebookにも同様の動画配信の機能が実装されています。
当初は、15秒ほどの短い動画の投稿ができることがひとつの特徴でしたが、現在は10分ほどの長めの投稿も可能になりました。
トークや対談の動画コンテンツというよりは「踊ってみた」や「歌ってみた」がその主流を占め、音楽を選択してSpotifyやApple Music などと連動していることも大きな特徴のひとつです。
TikTokのショート動画から大きなムーブメントになり、ヒットにつながる楽曲も生まれるようになりました。
▼SNS機能
動画に対するコメント機能や生配信の機能があるので、SNSとして相互に交流することも可能です。しかしながら、どちらかといえばYouTube同様にインフルエンサーとファンという関係性で成立する動画メディアとして認知される傾向にあります。
ただ、若者を中心に友人同士で「踊ってみた」や「歌ってみた」などの動画を発信して交流して楽しむという趣向もあり、若いユーザーにとってはエンタメ性の高い動画SNSとして人気があります。
▼デメリット
短い動画をユーモラス配信するエンタメ性の高いプラットフォームであるため、他のSNSと比較すると情報を動画で正確に配信するメディアには向いていないという見方もあります。
YouTubeのように正確でありのままの情報を長尺動画で配信するような目的ではなく、あくまで娯楽性の高いメディアとして利用する傾向が現時点では強い動画SNSとなります。
▼ビジネス面
TikTokで動画再生数によって収益化するには「Creativity Program Beta」というプログラムに参加する必要があります。ただし参加するには条件があり、その条件を満たしていないと参加することはできません。
<参加条件>
・18歳以上
・フォロワー10,000人以上
・過去30日間の動画視聴数100,000回以上
<報酬を得られる動画の条件>
・オリジナルかつ高品質・高解像度で撮影・制作され、編集レベルが高いもの
・尺が1分以上 他
その他にも生配信への投げ銭があるので、バズったTikTokerは投げ銭と企業案件によって稼ぐことができます。
他のSNSに比べてフォロワーが多い=バズるという方程式だけではなく、ひとつの動画だけ飛び抜けてバズることがあるのがTikTokの面白さでもあります。つまり、必ずしもフォロワーが多いユーザーだけがバズるわけではないので、ふとしたタイミングでバズって人気になる可能性を秘めています。
うまくTikTokユーザーのニーズにフィットし、ひとつの動画がバズることができればTikTokerとして稼ぐことができる可能性があるのです。
王道SNS
画像や動画とテキストを組み合わせて配信して、相互に日常の情報を共有することを主体とした大衆向けSNSについても解説をしていきます。

▼仕様
個人が、自分の日記や日々の出来事を発信し、友人や知人と交流する、いわゆる典型的なSNSとして多くの支持を集めています。世界で最も利用者の多いSNSであり、日本国内でも多くのユーザーがいます。
ストーリー機能やメッセンジャーによるメッセージのやりとりができる機能もついており、個人間の情報交換を行う場としては、理想的なプラットフォームとして活用されています。メッセンジャーには、写真や動画を添付し、電話をかける機能もついているため、コミュニケーションツールとしても有用とされています。
世界中に利用者がいるため、そのつながりは世界中に広げていくことができます。ただし、利用者同士は、基本的に承認制でつながるシステムであるため、YouTubeやTwitterのように一方的にフォローすることはできません。そういう意味では、本当に知人関係にある人同士が交流するコミュニティなのですが、その仕様も昨今のSNSの多様性に合わせて変容し、個々人の公開設定によって承認せずにフォロー関係を構築できるようになりました。
▼デメリット
前述したようにFacebookは多くの利用者が承認性で利用しているため、閉じられたコミュニティである側面があります。例えば、ビジネス利用のために個人ページを運用していても、どちらかというと友人単位のプラットフォームである認識が強いため、フォローがつきにくい傾向があります。
Facebookには、個人ページの他にFacebookページというビジネスや団体、イベント運営のためのページを作ることができるので、ファンページなどは別途運用するという方法もあります。
しかしながら、TwitterやInstagramに比べるとオープンなイメージが弱く、ビジネスに運用するメインプラットフォームにすると失敗する場合があります。
逆にコアなファンとコミュニケーションをとるサロンとして利用するインフルエンサーは多く、閉じられたコミュニティならではの運用方法があると考えられます。
また、視聴やいいねで収益化するシステムはなく、あくまでSNSとしての利用価値に比重を置くことで他のSNSと差別化をしています。
▼ビジネス面
前述したようにYouTubeのような再生数で収益化するようなシステムはないのですが、Facebookページをビジネスに運用する価値は十分あります。
インフルエンサーやタレントのファンページ、自社商品やお店のページなどを制作し、ファンや地域に向けてアピールすることで大きな宣伝広告効果があります。
また、個人ページでの収益化はできませんが、Facebookページには、動画に広告をつけて再生数に応じて収益化する機能があります。動画の長さは3分以上、Facebookページのフォロワーが1万人以上で、過去60日間の動画再生時間が、600,000分以上という高いハードルがありますが、条件さえクリアすれば、収益化できます。
あまり知られてはないですが、Facebookページの収益化同様にFacebookページ内でサブスク会員サービス(※利用条件あり)も提供できます。ライブ配信中の投げ銭機能「Facebook Stars 」も存在します。
あまり収益化のイメージがないFacebookですが、実はいくつかのビジネスチャンスがあり、クローズドなプラットフォームである方がむしろ有効であるとされるようなコミュニティビジネスに向いています。
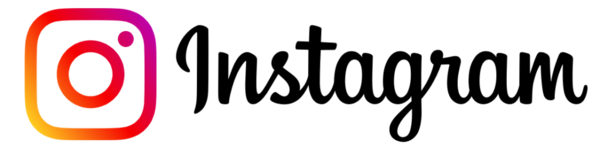
▼仕様
綺麗な写真、美しい写真、面白い画像など、画像と短い映像を主体として配信するSNSです。「インスタ映え」という言葉が流行語となるくらい絵になる写真を投稿することに特化しています。
ビジネスシーンにおいても、いかに「インスタ映え」をイメージして商品やサービスを提供できるかが、成功のキーポイントになっているほど多くのユーザーがいるのです。
Instagramは、画像の色調整エフェクトがデフォルトでされるのがひとつの特徴です。スマホで撮った多少色味の悪い写真もアナログ風のエフェクトやコントラストの強い色調整を加えることで、アートな作品に変換してくれるのです。
▼SNS機能
Instagramは、FacebookやTwitterのように個人の交流プラットフォームとしての機能性も高く、いいねやコメントはもちろん、DMやストーリーズ機能も備えています。承認性のコネクションではなく、フォローすることによってつながっていくSNSなので、オープンな不特定多数との交流にも有効的です。
そのため、タレントやインフルエンサーの利用者も多く、多くのフォロワーとつながるファンコミュニティとしての役割は非常に大きいと考えられます。
ファッション性やデザイン性が高いため、Twitterよりもビジュアルを魅せたいインフルンエンサーが利用する傾向にあります。同時にTwitter同様にハッシュタグを利用して情報を的確に拡散できる利点もあります。
インスタライブというライブ機能も備えており、配信中にフォロワーや友人とコラボできるという独特の生配信も人気があります。 Facebookを運営するMeta社が2012年に買収したため、Facebookとの連携が円滑になり、SNSを横断して利用する傾向にある現代のスタイルに適合していると言えます。
▼デメリット
Twitterほどには炎上のリスクは大きくないですが、画像や動画を投稿しているので、画像を悪用されたり、勝手に流用されたりするリスクがあります。
また、FacebookやTwitterと簡単に連携できることは、配信する側の負担を減らすことにはなりますが、個人情報を盗まれるリスクを増やすことにもなります。ひとつのSNSから漏れた情報がすべてのSNSに影響を及ぼしてしまう可能性があるのです。
▼ビジネス面
Instagramは現在、多くの企業やインフルエンサーが活用していますが、再生数や広告によるわかりやすい収益化はできません。
しかし、企業案件やアフィリエイトによって収益化することは可能です。商品の宣伝や販売サイトへ誘導することで収益を得ることは、一定数のフォロワーの獲得とブランディングの仕方によって実現可能になります。
また、ネットショップとの連携機能も強化され、画像に貼られたリンクから直接ネットショップの購入ページへ飛ぶことができるシステムも構築されました。
そのため、通信販売の広告と販売用のSNSとして実用的に利用する商店や企業が数多く存在するのです。
メッセージアプリ&SNS
メッセージ機能を主体にしながらも、SNSとしても利用できるプラットフォームについて最後に解説をしていきます。
LINE

▼仕様
SNSというよりは、チャットによってメッセージのやりとりを行うプラットフォームとして認知されているアプリです。
チャット機能と通話、ビデオ通話がついており、今や日本のスマホ利用者の9割以上が利用していると言われています。スタンプという独特の情感を表現するイラストやアニメーションを駆使した機能がついていて、ただチャットをするだけではなく、ユーモラスに喜怒哀楽を表現できるところが大きな特徴です。
写真や動画を添付でき、スケジュール管理機能やグループ通話も可能なので、プライベートな利用だけではなく、ビジネスシーンでも多用されています。
▼SNS機能
主にメッセージアプリとして利用する傾向にありますが、動画関連についてはLINE VOOMという投稿機能がついています。主にTikTokのようなショート動画を投稿しますが、長尺動画や写真、テキストの投稿も可能です。
LINEの友人関係になっていなくても、フォローすることで相互のやりとりが可能になります。日常で使用しているメッセージアプリなので、アプリを開く習慣の中に投稿を視聴するルーティンが組み込まれていると、多くの人がついつい利用するものです。 LINEの国内利用者数は、すでにTwitterやFacebookを遥かに超える人口がおり、国内SNSとしては最大と考えられます。世界基準である他のSNSに対して、国内シェアを圧倒しているLINEをいかに有効活用し、かつLINE自体がどのように変革を遂げていくかによって、今後のSNSの優先順位が変動していくでしょう。
▼デメリット
メッセージアプリとしては、他の追随を許さない人気を誇りますが、SNS機能としてはそれほど使用頻度が高くない傾向にあります。
テキストSNSとしてはTwitter、ショート動画SNSとしてはTikTok、日記型SNSとしてはFacebookのイメーが強く、LINEは記事投稿SNSとしての機能がそれほど明確ではありません。
「みんなが使っているLINE」というイメージで記事投稿をLINEでやっていても、実はリアルな知人に見てもらえない場合もあります。
LINEは投稿機能を通常のテキスト記事投稿からTikTok的なLINE VOOMに変更し、生配信のLINE LIVEのサービス提供を終了しました。利用していたユーザーからすると、せっかく時間をかけて増やしたフォロワーを失うことになります。
ビジネスで利用しているインフルエンサーや商用の宣伝に利用している場合は、仕様の変更に振り回されることで問題になることも考えられます。
▼ビジネス面
LINEはビジネスシーンにおいてもメールや通話をするコミュニケーションプラットフォームとして利用されています。昨今は、名刺にLINEのQRコードを表記して、スムーズなやりとりを可能にすることがデフォルトになろうとしています。
また、LINEには「公式LINE」という別アプリで、ビジネスやファンコミュニティを運営する際に使用するチャットプラットフォームがあります。個人で利用するLINEと違って、グループに対してのコメントの可否を制限したり、相互フォローされていなくてもチャットを視聴することが可能な機能がついていたりします。
個人情報を守りながらもファンとのやりとりを可能にする非常に有用なアプリとして多くのインフルエンサーや企業が利用しています。
X(Twitter)
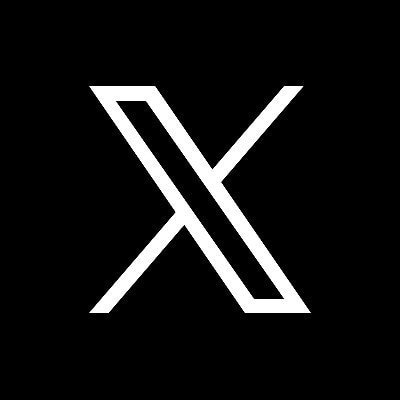
▼仕様
米国で発祥したテキスト投稿型のSNSです。全世界で約5億人以上の月間アクティブユーザーがおり、2022年まではTwitter.incが運営していましたが、2022年にPayPalやテスラを設立したイーロン・マスクが全株式を買収し、マスクが経営するXと合併しました。
初期の頃は、140文字という文字数制限がありましたが、現在は140文字以上でも投稿できるようになりました。Facebookのように承認制ではなく相互フォローをする必要がないので、オープンなSNSとして多くの情報が行き交います。
他人の投稿を自分のタイムラインでシェアすることをリツイートと呼び、多くのいいねやリツイートのある投稿は、より多くのユーザーに届くようになります。
投稿内に♯を単語の冒頭につけるとハッシュタグという機能が有効になり、検索結果に表示されやすいように設定することができます。
当初は、テキスト投稿が多かったのですが、最近は動画や写真の投稿も多くなり、他のSNS同様、時代のニーズの変化に応じて柔軟に対応していると考えられます。
Twitterは、広く情報を認知し、拡散する際に非常に有用なプラットフォームと言えます。マスメディアでは取り扱わないような現場のリアルな情報や裏情報、またそれらに関する意見を個人が不特定多数に向けて発信して同意や反論を得ることができます。
時に炎上のリスクがあることもありますが、それだけ情報の広がりが早く広いという特性があるのです。
▼デメリット
早く広く情報を拡散できるデメリットとして炎上のリスクがあります。ネガティブな評価が大きな話題になるとあっという間に拡散されてしまいます。
人の脳というのは、ポジティブな情報よりもネガティブでストレスフルな情報にアドレナリンをほとばしらせ、フォーカスしやすい傾向があります。トピックが刺激的であるほど、情報は拡散されて広まるのです。
世の中に週刊誌やゴシップ誌がなくならないのは、刺激的な情報に目を向けたくなるのが人の性だからなのです。それが有用である時もあれば、悪用されてしまうこともあるのがTwitterのデメリットとも言えます。
▼ビジネス面
情報の拡散効果が高いことから、企業やインフルエンサーが情報発信する際に、Twitterを多用することは多々あります。商材の販売やイベントの告知など宣伝広告プラットフォームとして利用するのに適しています。ただし、他のSNSに比べて炎上しやすい傾向もあるので、情報の内容にはとても気を使って配信する必要があります。
まとめ
今回は主要SNSの概要について触れましたが、SNSに限らず、ビジネス全般において動画のご活用にご興味がおありでしたら是非こちらからご相談ください!
▼株式会社LOCUSの会社概要資料のダウンロードはこちらから







